なくてはならないところに存在し、誰にも等しく、口を開けて待ってくれている。それがトンネルだ。でも私たちがそれに意識を向けるのは入る時ぐらいで、それからはあまり気を留めることもなく通り過ぎていく。トンネルがない世の中なんて、もはや誰にも想像できないのに。
空前の好況と人材不足というトンネルの先に、建設業界にはどんな未来が待っているのか。グローバル展開やICT化のトンネルをくぐり抜けた後、見える景色はどんなものなのか。
トンネルを掘り続けてきた匠、佐藤工業社長・宮本雅文氏に訊いてみた。
記事初出:『建設の匠』2018年12月25日
写真:奥村純一
橋梁志望者を虜にしたトンネル工事の魅力
「トンネル工事って、毎回の発破ごとに、見える姿が変わるんですよ」
宮本雅文氏は、トンネルの話になると途端に相好を崩した。
「掘っているとだいたい同じ岩質、地質が続くんですが、ひと発破ごとに点検に入ってトンネル先端の切羽(きりは)を見ると、それはまるで赤ん坊の顔のように変わって、にこやかな時もあれば、怒っている時もある。『この山は大丈夫やね』とか『山が苦しんでいるな』とか、なんとなく感じるんですよ。
トンネル工事というひと気のない山の中での作業ですが、草花や蝶などから自然の表情を感じ取り、同時に“危険”も感じられるようになりました。その域に達するのは、3現場目ぐらいですけれどね」
ひとたび語り出すと止まらない。新卒で最初に配属された現場の話になった。
「私はそんなに気にならなかったけれど、当時のトンネル工事の現場は空気が悪いし、暗いし、水は出るし、過酷な条件でした。そんなトンネルが貫通した瞬間に立ち会いました。
感激度は、人生の中で一番高かったですね。ものすごく昂ぶった。発破をかけると、煙がスーッとどちらかに流れていって消える。そこに光がスッと差し込んでくる。まるで日の出と夕日とがすべて一緒になったような感動は、山頂に登った時以上のものがあると私は思っています。……あんまり山登りしたことないけれど(笑)」

発注者も施工者も坑夫さんも、樽酒を割ってがぶ飲みしながら、一緒になって喜びを分かち合う。その現場の空気を肌で感じ、「トンネル工事って悪いもんじゃないな」と感じた宮本氏は、以来28年間、連続してトンネルの現場を渡り歩いた。まさに“トンネルの佐藤”の申し子である。
――とは言いながら、実は橋梁を架けるほうに興味を持っていた、と述懐する宮本氏。大学時代は土木工学科で橋梁の勉強をしていた。卒業は1974年、折しも田中角栄の日本列島改造論がぶち上げられ、日本中でインフラ整備が盛んに行われている頃だ。
「これからの世の中は建設業だ、土木だ」と考えていた若かりし頃の宮本青年にとって、就職先はどの建設会社でもよかった。縁あって佐藤工業から声がかかり、「当時、グループ会社に橋梁部門もあるし」という軽い考えで入社を決めたのだという。それからトンネルにハマった経緯は、前述の通りである。
「そんなに詳しく調べずに入っちゃって」と宮本氏は屈託なく笑う。率直さと正直さが魅力的な人、というのが第一印象だ。
聞け、山の声を
黒部トンネルや東北新幹線第2上野トンネルなど数々のトンネル難工事をこなし、掘削精度や距離の日進・月進記録などの面で高い技術力を誇る佐藤工業は、“トンネルの佐藤”という二つ名を持つ。
「当社が“トンネルの佐藤”と呼ばれるようになった礎を完全に築いた場所が、黒部だと思います。ただ、歴史を紐解くと、当社のスタートはトンネルじゃない。河川改修と橋なんです。日本が近代国家へと歩む中で、道路・鉄道・電力工事と業容を拡大していくとともにトンネルの実績が増え、当社がそれを得意としていたことから、黒部の工事で声をかけられた。
また当社の場合は北陸の富山発祥で、粘り強く、雨や雪にめげずに働く人たちがたくさんいます。彼らが全国のいろいろな現場へ行っても高い評価を受けてきたからこそ、当社は成り立ってきた。いまでも『トンネルは(佐藤工業に)任せれば大丈夫だ』というお客さんはたくさんいると思います」
真面目で勤勉、辛抱強いといわれる富山県人の気質こそが、佐藤工業の原動力か――と納得していたら、宮本氏が「私は富山県人じゃなくて、和歌山県の出身ですけどね」と二カッと白い歯を見せて笑う。
そんな佐藤工業で、トンネル工事の“匠の技”はどのように育まれるのだろう。
「私も若手の頃、仕事で写真を撮ったりスケッチしていました。ひと発破ごとに1~2回はスケッチを描くんです。そんなにスケッチの才能ないんですけれど(笑)。でも描くことで、感じることがある。変化が分かるようになる。そのようにして山とコミュニケーションを図るというか……」
山の表情の変化や山が発する声は、誰でも感じ取れるようになるのだろうか?
「当社にはだいぶ成長してきたトンネル技術者がいて、それは他社に比べて(割合として)多いと思う」と宮本氏は前置きしつつ、こう付け加える。
「当社の若い社員は測量や記録のために現場に入りますが、その領域(山の表情の変化や山が発する声を感じる)にはなかなか達することができない。一方で、坑夫の方にはそれを感じる人たちがたくさんいます。“先山(さきやま)”と呼ばれる山の先を読む人たちは、自分たちの命を賭けて現場に接しているのだから。私は彼らを大事にしていますし、彼らの意見を聞きたくて現場に行き、彼らと必ず話をしています」
山との対話ができるようになる――それは社員の研修マニュアルに箇条書きでまとめられるようなものではない。言語化しがたく、伝承が難しい技術だ。宮本氏も「それが悩み。いま試行錯誤している」という。トンネル作業員が先山として一人前になるのは、15~20年の経験が必要なのだとか。
だからこそ、社長みずから行動して現場へ行き、切羽の声を感じたいと思っている。
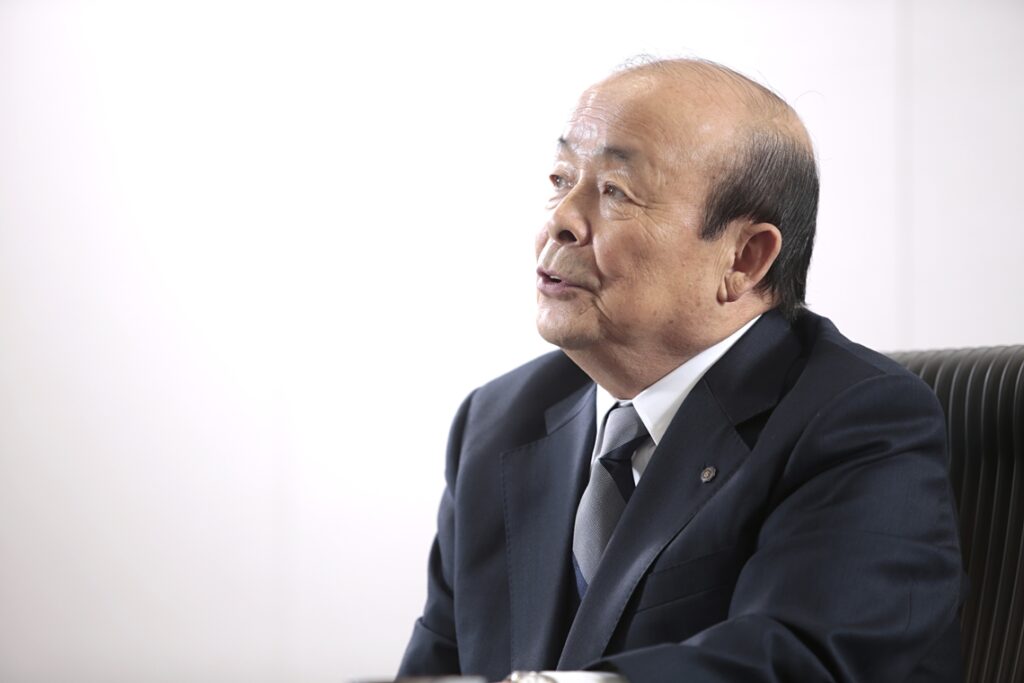
「私はいま現場に行ったら、昔の坑夫の仲間が何人かいるので、まず真っ先に彼らのところへ行って『元気にしてるか』と声をかけに行きます。その姿を当社の社員に見せる。作業員もそれを意気に感じて一生懸命働き、いい仕事をしてくれる。それが好循環につながっていけばいいなと思います」
しかし一方で、「これまでトンネルの掘削技術はちょっと特殊で、ある意味で我々の専売特許でした。それがいまやトンネルの安全技術はある程度確立されていて、シールドマシンで掘ればすごく高い安全性が確保できるようになり、当社の優位性が薄れてきている」と、宮本氏は少し寂しそうな顔を見せた。
リニア中央新幹線の山梨・静岡工区という大工事に参画しているとはいえ、“トンネルの佐藤”が国内のトンネル工事をメインフィールドにしていくにはやはり限界もある。
そこで、仕事を広くグローバルに求めていくことになる――。
海外展開における現地との向き合い方
とは言えども、佐藤工業は、比較的長く海外展開に取り組んでいる会社である。
ことシンガポールにおいては、40年以上の歴史を持つ。展開の発端はマレーシアだったが、いま主に取り組んでいるのはシンガポールの土木工事だ。建築案件はシンガポール、マレーシア、タイ、カンボジア、ミャンマーなどで展開しているという。
日本のゼネコンが海外で成功を手にする術を尋ねてみた。
「たとえばシンガポールでは、現地社員をコンスタントに抱えられる会社になることですね。1年ごとに職を変える“ジョブホッパー”といわれる彼らに、選ばれる会社にならないとダメでしょう。彼らには高額の報酬を用意すれば間違いなく残るんですが、それはなかなか難しい。そこで『他社へ行けば報酬は高いけれど、こういう仕事はできないよね?』と気持ちをくすぐるんです。自分たちが施工したものに対する達成感や自己満足度が高ければ、残ってくれる可能性が高くなる。個人のやりがいをうまく捕えればいいんじゃないかな、と」
宮本氏は何度も「建設工事はひとりではできない」と口にした。

彼が建設業界入職時に「会社にはこだわらない」と考えたのも、チームワークの仕事であり、大プロジェクトは工区の中に多くのゼネコンが参加していて、そこでなかよくしながら、時にライバルとして一緒に技術を磨くもの――そんな思いあってのこと。たしかにその意味では、どの会社に入っても一緒かもしれない。
「もともと、我々のようなゼネコン社員だけで、ものはつくれない。つくる職人がいてはじめて成り立つ。ケンカする時もあるけれど、職人と会話をして、彼らがいつも最大限に気持ちよく、プラス思考になるような形で接して、いいものをつくりたいという気持ちで取り組めば、建物でも土木構造物でも、みんなの気持ちが入る。その成果を、お客さんは間違いなく認めてくれます。国も言語も、関係なく」
宮本氏は、自信を持って力強く言い切った。
ゼネコンが海外展開すると、商慣習の違いに戸惑うことが多いという話はよく聞かれる。場合によっては不利な契約を締結してしまい、大きな損失を負うこともある。
「国によって契約内容を吟味しないといけないんですが、日本人はこれまで口約束でやってきたので、それがなかなかできなかった。日本企業と海外企業で合弁会社をつくっても、日本のノウハウを吸収し軌道に乗ったら、独立する企業もあるといいます」
昨日の友は今日の敵、まさに生き馬の目を抜く世界。これまでアジアを中心に海外事業を展開してきた佐藤工業はと聞くと、「シンガポールでも、うちの協力会社として技術指導して、一緒に成長してきた会社が、当社とほとんど同レベルのものをつくるようになり、いまや競争相手になっている」と宮本氏。
海外と言えば、打って出ることだけがグローバル化ではない。人材を迎え入れていくこともまたひとつのグローバル化だ。おりしも改正出入国管理法(入管法)が可決され、建設業界に外国人人材が増えていく局面を迎えることになった。多様な人材をいかに活用し、日本の建設業の匠の技を伝承させていくか。そして、建設業界の働き方を変えていくことができるのか――。
後編では、佐藤工業の“次の一手”に迫る。

