コンクリート製の巨大な堤体。広く深々と水を湛えた湖。大迫力の放流――。
多くの匠の技によって建造されたダム。そのスケールはいわゆるダムマニアをはじめ多くの人を魅了してきた。

しかしその人知を超えた迫力、または自然環境保護の観点から、ダムに対して否定的な意見があるのもまた事実だ。2019年秋に日本列島を襲った台風19号においても、ダムに対する肯定・否定さまざまな言説がメディアを賑わせた。
気候変動、地方創生、インフラツーリズム――令和のダムを囲むキーワードはさまざまだ。ダムはこれからの世界にどう共生していけばいいのだろうか?
ところが一般財団法人ダム技術センター理事長・川崎正彦氏に話を訊いたら、どうもそんな次元の話ではないらしい。
ダム建設技術の伝承に、危機が迫っているというのだ。
記事初出:『建設の匠』2020年2月27日
写真/編集部、ぱくたそ、奥村純一(首都圏外郭放水路)
ダムは世につれ世はダムにつれ
旧建設省でダムを担う河川局開発課や各地方整備局を渡り歩いてきた川崎氏。地方自治体の役所や環境省などにも出向したこともある。「ダム技術センター理事長」の堅苦しい肩書きのイメージを裏切る軽妙洒脱な語りで、ダムを取り巻く戦後の時代背景を解説してくれる。
「戦後の復興に合わせて、ダムはまず発電用として、電力の確保が求められました。それから農業の生産量を増やすために農業用水のニーズ、製鉄業など工業用水のニーズが高まってきた。さらに人口が増え、都市に人口が集中するにともない、水道用水を確保し、計画的に給水するために水道が整備されるようになりました」
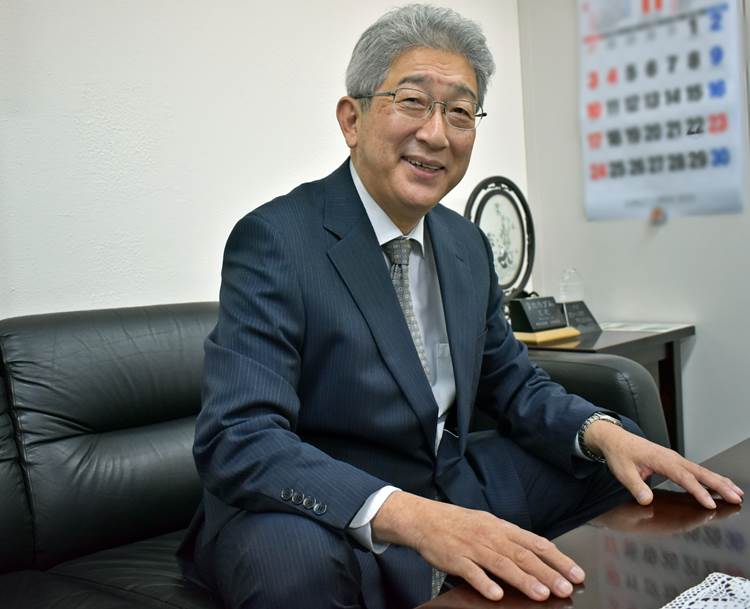
しかし狭い日本の国土において、ダムサイト(ダム建設用地)は限りがある。そこで発電、そして農業や工業用水などのいわゆる「利水」のニーズを叶えるため「多目的ダム」として新規開発されることに。
そんな状況が戦後から長く続いた。が、しかし。
「技術の進歩で工業用水を回収できるようになって、同じ水を30回も使えるようになった。さらに産業の形態が変わっていき、水を使わない産業が大きなシェアを占めてきた。だから水を使う用途がどんどん少なくなって、工業用水が余るようになったんです」

生産過程で大量の水を必要とする重工業から、純度の高い水を少量だけ用いる精密機械工業へ――。そして、水道用水についても2008年に日本の人口はピークをむかえた。大都市ではまだ人口は増えているが、水需要が伸びなくなった。ご存知のように、トイレやお風呂、洗濯機などは節水機能が整い、ひとり当たりが使う生活水量が減っていったのだ。
時代とともに水のニーズ、取り巻く環境は変わってきたと川崎氏は語る。
「2018年に水道法が改正されました。民営化も話題だけれど、要は水道の目的を変えたんです。水道は基本は市町村単位に委ねられていて、小さい町村の事業所では事務員2、3人で運営しているような小さくて経営基盤の弱いところが多い。だから経営基盤の強化を目的として、事業を合併し大きくして、職員数も確保するなどの方向に変わっていかねばならない。量を確保して給水区域拡大を目的にする水道の時代ではなくなったんです」
そして、今度は気候変動の波がやってきた。記録的な豪雨による河川の氾濫や市街地の冠水など、かつては東南アジアでしか見られなかったような光景が、いまや毎年のように国内で報道されている。
「温暖化が進展すれば、おそらく、いまの新潟や秋田とか、ちょっと寒い地域で現在は稲作の中心となっている土地での米づくりは厳しくなってくる。降雪量が減少し、田植えに必要な雪解け水が不足し、気温が上がって稲作の適地が変化し、将来は北海道あたりが中心になるのではないか」と川崎氏はみる。

地球温暖化によって寒冷な地域が北にスライドしていく。当然、それにともなって農業が変わる。また、温暖化により大雨が多くなる。これは短時間に降る豪雨の代わりに、雨が降らない期間が長くなることを意味している。
「2016年の利根川水系での渇水がそうなんだけど、温暖化が進行すれば山に雪が溜まらない。利根川などでは、冬のあいだに降った雪が解けた水をダムに貯めて、1年間使っているわけですよ。冬に雪が降らなければ、ダムに水が貯まらない。夏場に雨が降らなければ、渇水になってギブアップです」
そしてもうひとつは、と川崎氏。
「……東日本大震災です。あれでエネルギー政策が見直された」

震災後、原発依存低減や化石燃料使用量を減少させ、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを積極導入することになった。それで住宅用太陽光発電なども一気に普及した。
しかし太陽光発電は夜間に発電できない。供給電力の変動幅が大きいのも課題である。安定性のある基礎発電としては原子力発電(+揚水発電)の方が上だが、変動が少ないという面では水力発電もそうで、水力発電は短時間のうちに出力を上下できるメリットがあると川崎氏は語る。
ただし農業用の水路等を利用した小水力発電はたくさんできても、新たな大規模水力発電は難しい。
つまり、水道や工業用水、発電等の水利用が大幅に伸びる要素は少なくなっている。そこで川崎氏は「今後も、ダムの需要があるのは治水枠です」と断言した。そう、限りあるダムサイトを活用した既存ダムの再開発だ。
これがダム技術者の生きる道?
放流設備を増設したり、土砂堆積を防いだり、あるいは堤体そのもののかさ上げをおこなったりする。それが「ダムの再開発」だ。
![]() 【参考記事】萩原雅紀のダムライターコラム【4】バージョンアップで復活!不死鳥のダムたち
【参考記事】萩原雅紀のダムライターコラム【4】バージョンアップで復活!不死鳥のダムたち
建設当時より雨量が増えたのなら、それに対応できるように流せる水量や貯められる容量を増やせばいい。話は実にシンプルである。
しかし、いざ建設となると簡単にはいかない。「すでに水が貯まって利用している」ことがネックになるのだ。
ダム新規建設の際はトンネルを掘り、河川の流れを付け替える。そうなればダム建設予定地は水のないドライな状態。ある程度の自由度をもって施工できる。

しかし再開発はダムを運用しながらおこなう。常に水を貯めてある状態だ。洪水調節や利水補給などの機能を保持したまま、たとえばかさ上げ工事をしなければならない。
「その状況でダム本体に穴を空けらなければいけない。下手に空けたらダムの水が抜けてしまうので、上部に蓋をして止水する技術が必要」と川崎氏。
その際に工事を担うのは潜水士だ。場合によっては100m近く潜り、高い水圧がかかる水中で作業をおこなう。昨年、水力発電施設を点検しようと潜水し、導水管に右腕を引き込まれて不幸にも亡くなった作業者の方がいたが、このように技術を持った人もまた、かけがえのない存在である。
なにより時間のかかるダムの建設工事ゆえ、その状態をキープするのも大変。……考えるだけでも難易度は高そうだ。

「工事が難しいんですよ。それにいかに治水目的と言えども、下流の利水者や発電の関係者たちと調整をしないと再開発はできない。彼らをフォローしながら一緒に動いていかなければならない時代に入っています」
施工計画の立案も骨が折れる作業だ。なんせ最終設計図だけではどうやってつくるか判断できないことが多すぎる。施工⇔設計のこまめなやりとりによる設計・施工の図面制作がマストになってくる。
ちなみに海外ダム事情はというとまだ新規開発が主流で、「ダムの再開発」は国土の狭い日本特有の課題だとか。参考となる事例もなく、一つひとつ条件が違うダムを対象に、日本の技術者は独自に知恵を絞らねばならない。もちろん某バラエティ番組のごとく「ダム(湖)の水ぜんぶ抜く」わけにもいかない。そして追い打ちをかけるように……。
「ダム技術者が、他方面に引っ張られているんです」
川崎氏はおもむろに眉間にしわを寄せた。

ひっぱりだこのダム技術者
いま、ダム技術者が不足する事態が迫っているというのだ。……いったいなぜ?
まずは、国や都道府県のダム建設をおこなう民間のダム技術者について見てみよう。ダム建設に関わる管理技術者には「CMED」という資格が必要だ。
「ダムを安全につくっていくように、建設大臣の認可によるダム工事総括管理技術者(CMED)制度が1987年に創設されました。これは土木分野における最難関試験です。まず受験資格が大変で、ダム現場で10年以上、ないしはダム現場を7年含む土木現場15年以上の経験がなければ受験できず、いちばん若い大卒者で32歳から。いわば“現場第一主義”の資格です」
「土木分野の最難関」という川崎氏の言葉に「えっ? あのコンクリートのダムをつくるのって、橋やトンネルよりも難しいの?」と意外に感じられる方もいるかもしれない。

実はダム建設においては、沈む町に替わる町の造成のため、新たに仮設道路も橋もトンネルも宅地も、すべて建設する必要があるのだ。また、ダム本体の工事も、圧倒的スケール感と計画の緻密さを併せ持つ仕事だ。「その資格を取った技術者は、フィルダムだと400~500万トンぐらいの土を動かし、400~500人の作業員をたばね、年間100~200億円を使う現場でもひとりで全責任を負って施工管理できる、他に類を見ない技術レベルの仕事」だと川崎氏。

そんなCMEDの試験は、相当の難易度だ。
「2次試験などはどこぞのダムの発注図面をポンと渡されて『午前10時から午後5時までのあいだに、リフトスケジュールや機械設備の配置などすべての作業を含めた施工計画をつくり、工期計算しなさい』。これは大変ですよ。さらにその後は大ベテランのダム技術者がつとめる面接官に『なぜこんな数字なのか。この工程は長すぎるのではないか』『このバケットは何トンで計画してるのか?』などと突っ込んでくるのに対し、100点の答えはないにしても『私はこう考えた』と理由を説明しなければいけない」
CMEDには2020年1月までに822人が合格し、現役資格登録者は516人だとか。その内訳は「すべてゼネコンの中の人」。発注者も建設コンサルタントも受験できない。ダム現場に行っているのはゼネコン社員しかいないからだ。
そんなCMED有資格者はゼネコン各社の垣根を超えて、持てる情報や知識を共有し合うほどに仲間意識が強い。そういえば飛島建設社長の乘京氏もそう語っていた。しかしやはりというか、高齢化が悩みのタネ。今後は年間20~30人が現役から抜けていく算段だという。
彼らの技術力が求められる場。それはたとえば、東北の復興現場だ。被災した町自体をかさ上げし、堤防を築く。工場や設備の設置方法や資材を運ぶダンプトラックの大きさ、ベルトコンベアで運ぶ際の想定――そんな工事は、ダム建設と同じでダム技術者の活躍の場である。無から巨大構造物をつくられる彼ら技術者の力がフルに発揮されるのは喜ばしいことだ。
しかし、昨今の技術者不足のなかで、その技術の高さが仇となって支店の幹部は復興現場のCMED有資格者を手放さず、彼らはダム建設現場に戻ってこれない。一方で気候変動によって災害が頻発し、全国各地で災害に強いまちづくりをしようということになれば、ダム技術者は今後ますます被災地復興にひっぱりだこになるだろう。
ダムの新規建設が少なくなる2020年代。「受験資格を満たすために必要なダム現場の経験が不足する」時代が、やがて到来する。そうなれば10年~20年後、ダム再開発にともなうダム技術者の需要は増すのに、育成の場がないために人材供給ができなくなるのだ。
ダム発注側も人材不足の時代へ
「今後、技術の伝承はしんどくなると思います。まだゼネコンにはCMEDが500人いるから、現場でダム工事をおこなう技術者はまだそこまで減っていない。ところが発注側の技術者が減っている」

元官僚の川崎氏ならではの重い発言だ。ダム建設を担当してきた優秀な技術者が大量に定年退職を迎え、ダム事業数の減少から若手技術者がダム技術を習得する現場がなくなっているという事実――。
そもそもダムをつくる際、発注側の努力にはあまり目を向けられない。最初に計画をつくり、地元市町村の了解をもらい、地元に入って交渉しながら用地を譲ってもらう。生活再建のために代替地を造成する。それから付替え道路工事がはじまっていく。道路工事が終わってから、ようやく本体工事がはじまる。ダム本体工事の前にやるべきことはたくさんある。
「発注者目線で言うと、ここで仕事は8割終わっている。技術的におもしろい2割(堤体などの工事)をゼネコンの人たちが受注してやっている」と川崎氏。また、ダム本体工事の設計図や工事の仕様をとりまとめて発注するのも発注側技術者の仕事だが、彼は「発注前の仕様書づくりが一番おもろい」と言い切るタイプの人だ。
発注側のダム技術者を育てるためには、やはりダム現場で自分の手を動かし、経験を積む必要があるという。しかし繰り返すが、国や都道府県の新設ダム事業は数えるほどしかない。
こうして発注側の若手技術者の育成とダム技術の伝承はどんどん難しくなる。そんな状況のなかで今後再開発できる人材を育てていかねばならない――。
ダム管理業務においても同じことが言える。
「ダム管理でもダム建設技術の知識は必要です。管理していれば『漏水が増えたか減ったか』『異常はなぜ起きたのか、堤体に問題があるのか違う原因なのか』を探らないといけないでしょう。ダムを建設する際にこんな技術的な苦労があって、こんなところに気を付けなければあかん……という知識がないと、なかなかやりにくい」
前述のように再開発を迫られるダムで、担当がダム建設を経験していない若手職員だったら……たとえ申し送り事項があっても、途方に暮れてしまうのではないか。
昨年10月に試験湛水をはじめた横瀬川ダム(高知県)は、四国においては約20年ぶりの新規ダム建設だった。そのためダム技術のノウハウ伝承で苦労し、ダム技術センターも支援するなどの対策を講じたそうだ。実際、ダム建設がいったん終わった国土交通省地方整備局が出てきている。今後、各地で再開発がはじまると、同様の問題が表出してくるだろう。

さらに言えば、建設中の安威川ダム(大阪府)と鵜川ダム(新潟県)を最後に、日本のロックフィルダム建設は終わる。技術革新により、築堤材料の合理化が可能なCSGダム(Cemented Sand and Gravel)建設が中心になってきている。
ダム建設の絶対数が少なくなったいま、CSGダム建設を経験していないゼネコンも多い。またICT建機による無人化施工など高い技術力でもって数多く受注できるゼネコンがある一方で、ダム建設入札から手を引かざるを得ないゼネコンもあらわれている。「企業努力の結果」といえばそれまでなのだが……。
治水の話に戻そう。川崎氏いわく「治水というものは、水系によってベストなものが違うんですよ」。たとえば利根川と淀川、筑後川の治水対策はまったく別物。その上でダムと河川改修、遊水地や放水路などの組み合わせから「いちばん安くて、効率の上がる治水のかたちを探していく」のだそう。だからよく言われる「ダム建設ありきの治水だ!」ではない。
「まちの直上に広い遊水地があるなら遊水地が担えばいい。放水路が効率よければ、その役割を負えばいい。引堤ができる地域は、それをやればいい。一番いいものを選択すればいいんです。それらで足りるなら、別にダムは要らないですよね」
ちなみに「引堤」とは、川の流下能力を大きくするため、家屋や用地を買収して、川幅を拡大し既設の堤防を堤内地側に移動させることだ。

「ダムなど不要だ、代わりにスーパー堤防を整備せよ」という言説も見られる。しかし治水はダムや遊水地、調節池や放水路、そして堤防などの中から資産や立地条件等を見て総合的・一体的におこなわれるもので、「ダムよりスーパー堤防」という単純な話ではないという。
実際のところ、「改修のために一度引堤(ひきてい)をして家をすべて動かした場所の再引堤はさすがにむずかしい」と川崎氏。そりゃそうだ。これから人口がますます都市部に密集するというのに、住民への説得や補償をおこなっていたら一生終わらない。
仮に昨年越水した多摩川周辺にスーパー堤防を整備しようと、密集した住居をごっそり移すことになる。それが現実的かと聞かれれば、誰もが首を横に振るだろう。なんせ一部に「景観を楽しめない」という理由で堤防さえもなかった地域もあるぐらいなのだから……。
首都圏には“地下神殿”と呼ばれる首都圏外郭放水路や神田川・環状七号線地下調節池、いわば地下のダムがある。用地買収の必要がなく、効果も高い。同種の施設は大阪にも建設中だ。ただ、地下の建設にはかなりの時間を要するし、費用も相当なものである。

環境や費用、効果などを鑑みた消極的な理由からも、ダムはコスパがよく比較的建設しやすい、と言える。
それでも、ダムはずっと不遇をかこつ存在だった。
誰のためにダムをつくるのか
かつて黒部第四ダムや佐久間ダムの建設記録映像を観たとき、作業現場の危険さや特撮映画のような大発破(火薬でダムサイトの岩石を破壊すること)にとにかく驚いた。
おそらくダムが全国にたくさんつくられている頃は豪快に発破し、全国から集まった怖いもの知らずの猛者たちが夜間も働いていたのだろう。命にかかわる事故も少なからずあった。そして建設ラッシュの時代には巨額のお金が動く。お金に群がる輩による汚職事件などもあっただろう。
……ひるがえって2020年のいま、ドッカンドッカンとダイナマイトでぶっ飛ばす建設工事など絶対にできない。「火薬の量をできるだけ減らし、音や振動を出さないような発破」をしているそうだ。高低差があるブロック工法から平面作業のRCD工法になって落下死亡事故が激減し、談合も官製談合防止法で禁止されて久しい。
「昔はとにかく短時間で建設するのが効率がいいと言われてきた。当たり前だけれど、いまの方が昔に比べてはるかに制約条件が多くなっている。いまは土地を提供していただくと同時に、周辺の生活基盤をつくるためりっぱな道路も、生活再建支援策もつくらなければいけない。ダムをつくる際に補償金を払うだけでおしまい、ではダメなんです」
ざっくり言うと巨額の事業費の3分の1は用地補償や生活再建に費やされ、3分の1が道路付替え費、ダム本体工事に使われるのは3分の1ぐらいしかないらしい。そびえ立つダムは、思ったよりも配慮のカタマリだった。

それでも、ダムはなかなか存在を認められない。
ダム建設最大のネックは、自然環境保護対策だ。
「ダムが自然環境にまったく影響を与えないとは言えない。流水型ダム(自然⇔河川の標高に穴が空いているダム)等でなければ魚の行き来もできなくなるし、どうしても自然環境は変えてしまうんです。だから自然環境保護の観点だけで見られて、ダムは批判されてきた。治水や水道などの水利用をわれわれの暮らしと河川環境を含めて全体で考え、対応策を示し、ダムをつくる際にも最大限の環境対策をおこなってきた」。川崎氏は渋い顔でそう漏らす。
自然環境保護――。「本気で自然環境保護をしようと思うなら、人類は滅びるしかないのではないか」。高校生の時の筆者はそう考えていた。国連で「あなたたちを許さない」とオトナを批判する某女史も顔負けの暴論だ。
さすがにいまは、そんなことは思わない。人間は知恵を絞って、現代文明の維持と自然環境保護の妥協点を探るしかないと思う。実際にダムは自然環境にできる限り配慮しながら、下流に住む業の深い人間の暮らしを守るために存在してくれている。
自然環境や地域住民に少なからず伴う犠牲。ふるさとから離れなければならない人たちの痛みや哀しみも、ダム関係者であればすべて百も承知だろう。こうして建設されるダムは、自然環境と人間の便利な暮らしの妥協のカタマリでもあるのだ。
ダムをつくる人、まもる人に敬意を
どれだけ技術が進歩しようとも、ダムは墨俣一夜城のように短工期ではつくれない。長い年月をかけて周囲に配慮しながら粛々と建設しているあいだに、水のニーズ変化や気候変動が起きて「もう需要がなくなったから要らない」と言われても困るというものだ。
長い建設計画の最中には必ず反対運動が起きて、政局次第では計画見直しさえ起こりうる。名建築家のように、建設にたずさわったダム技術者の名が語り継がれるわけでもない。
調整と説明と配慮と妥協――ダム技術者は本当にストレスフルだよなあと勝手に心配になる。挙句の果てに苦労してつくったダムに対し「不要論」まで叫ばれた日にゃ、心が折れてしまうのではないか。「自分たちはそんなに悪いことをやっているのだろうか」と……。
ダムを長らく見守ってきた川崎氏が強い衝撃を受けたのは、ダム賛成・反対の次元を超えた第三極・ダムマニアの登場だ。これまでダムは賛成か反対かと叩かれてきたが、いまではダムを素直に楽しんでいる人々がいるのだから。
台風19号時のただし書き操作や八ッ場ダムの件では、大手メディアのダム報道に対し、データで持って冷静に「ダムはこんなにがんばっていた!」と異を唱えたり、日本ダムアワードで讃えたりしていた。そんなダムマニアの存在に、勇気づけられたダム技術者は相当多いはずだ。
 日本ダムアワード2019のようす
日本ダムアワード2019のようす
当メディアでもおなじみ萩原雅紀さんはダムマニアのパイオニア的存在だけれど、みずからダム動画を制作・配信するなどして、ダムビギナーへの門戸を積極的に開いている。それは若い世代へダムの魅力と意義を伝えていかなければならない、という使命感あっての行動だろう。
実を言うと筆者は、かつてダムが苦手だった。
幼い頃は放流サイレンを怖く感じたし、底知れぬダム湖のそばを自家用車で走るときには身がすくんだ。また、長良川河口堰建設問題報道で揺れる中部地区にて「自然環境を破壊してまで建設する必要あるんか?」と疑問を持ちながら育ってきた。
しかし、このメディアを通じてダムやダムマニアのみなさん、ダムの中の人たちと触れていくにつれて、ダムに対する恐れや誤解は薄れ、ダムの魅力を感じられるようになった。
ダムの役割や力、それをつくる技術、そしていまのダムの限界――。わたしたちはそれを正しく理解し、適切なかたちで伝えていかなければならないと強く感じる。

川崎氏はダムに対する想いを込めて、こう語ってくれた。
「ダム技術者はみんな、ダムがおもろいから、やっているんです。おもろくなかったらやらない。それで自分が一生懸命つくったダムが地元の人に『ありがとう』と言われたら、すごく嬉しいの。『ありがとう』なんて言われたら、もうたまらんよ。地域や人とのつながりもおもろいと思って、やっているんです」

インターネット界隈やリアルワールドで、ダム好きを自称する子供たちを見かけると嬉しく思う。彼らがいつの日か、「ダムをつくる人」の側にまわってくれたら……そう願ってやまない。そしてその日まで、誇り高き「おもろい仕事」であるダム建設技術の火を、我が国から決して絶やしてはならないのだ。

